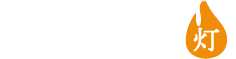今年の冬は寒さが厳しく、暖房器具なしでは快適に過ごすのが難しくなっています。
しかし、暖房器具に頼りすぎると、体が本来持っている体温調節機能が低下し、冷え性や血行不良などの不調を招くこともあります。
そこで今回は「温活(体を内側から温める健康習慣)と暖房器具の関係」について解説し、冬を健康的に乗り切る方法をお伝えします。
温活とは

温活とは、体を冷やさないように工夫し、血行を促進することで健康を維持する習慣です。
体の熱は血液によって全身に運ばれているため、血流が悪くなると体が冷えやすくなります。
冷えによる主なデメリット
- ・血行不良による肩こり・腰痛
- ・免疫力の低下
- ・基礎代謝の低下
寒さを感じると体は体温を維持するために血管を収縮させ、血流を抑えて熱を逃がさないようにします。
しかし、冷えが続くと血流が悪化し、さまざまな不調を引き起こす原因になります。
逆に、適度に体を温めると血管が拡張し、血流が良くなるため、体の調子が整いやすくなります。
現代人の体温の低下

現代人の平均体温は昔と比べて低下していると言われています。
その原因の一つとして、暖房器具の普及による体温調節機能の低下が挙げられます。
体温低下の主な原因
- ・ストレスの増加
- ・運動不足
- ・食生活の乱れ
- ・暖房器具の過剰な使用
暖房器具を過剰に使いすぎると、体温調節機能が鈍くなり、自律神経の働きが乱れることがあります。
自律神経のバランスが崩れると、不眠や疲労感、無気力感など精神面にも悪影響を及ぼします。
▼関連リンク
今話題の”温活”で冷え改善!!自律神経を整えるオススメの対策方法とは??
温活と暖房器具の正しい付き合い方

寒い冬を乗り切るためには、暖房器具を適切に使いながら、自律神経を整え、体温調節機能を維持することが大切です。
暖房器具の種類と特徴を理解する
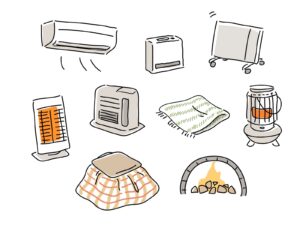
暖房器具にはさまざまな種類があり、それぞれに特徴や適した使い方があります。
自分の生活環境や使用目的に合ったものを選ぶことが、快適かつ効率的な温活につながります。
一人暮らし・狭い部屋向け
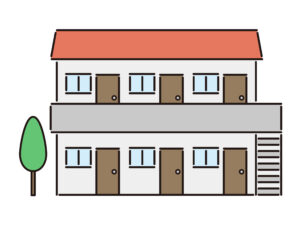
■電気毛布
寝る時に最適で、電気代が安く、ピンポイントで温められる。
ただし、長時間の使用は乾燥しやすく、低温やけどに注意が必要。
■セラミックヒーター
即暖性があり、足元や手元をすぐに温められるため便利。
ただし、電気代がやや高めで、部屋全体の暖房には不向き。
■こたつ
長時間座って作業する人に向いており、省エネ性も高い。
しかし、動かなくなりやすく、寝落ちすると風邪や低温やけどの原因になるため注意。
家族暮らし・広い部屋向け

■エアコン
部屋全体を素早く暖められ、効率が良い。
ただし、乾燥しやすく、風が直接当たると体感温度が下がることも。
加湿器との併用がオススメ。
■オイルヒーター
音が静かで空気を汚さず、乾燥しにくいのが長所。
一方、暖まるまで時間がかかり、電気代もやや高め。
さらに、本体が重く移動しにくい点も考慮が必要。
寒冷地向け

■寒冷地仕様エアコン
通常のエアコンより暖房能力が高く、雪国でも活躍。
ただし、通常のエアコンより価格が高い。
■石油ストーブ
停電時でも使え、しっかり暖まるのが魅力。
ただし、灯油の補充が必要で、火を使うため換気や安全管理に注意。
コストと使いやすさのバランス

寒冷地以外では、エアコンが最もバランスの取れた暖房器具です。
効率が良く、ランニングコストも比較的抑えやすいですが、乾燥しやすいため加湿対策が重要です。
寒冷地では、寒冷地仕様エアコンや石油ストーブを併用すると、効率よく暖を取れます。
生活環境や電気代の状況に応じて、最適な暖房器具を選びましょう。
暖房器具の設定温度を見直す
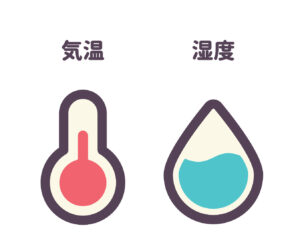
”室温が18〜22℃になるように暖房の設定温度を調整する”のが理想的です。
特に寒い時期は、暖房を高温に設定しすぎると室内外の温度差が大きくなり、自律神経の乱れや体への負担につながることもあります。
また、体感温度を上げる工夫を取り入れることも大切です。
例えば、加湿器を活用するなどして部屋の湿度を40〜60%に保つと、暖房の設定温度を下げても快適に過ごしやすくなります。
また、部屋の空気を循環させることも、暖房効率を高めることができます。
▼参考リンク
部屋の温度は何度が理想?適温と室温の違いは?(外部リンク)
家の中の寒暖差を小さくする

リビングだけを暖めすぎると、浴室やトイレなどとの寒暖差が大きくなり、ヒートショックのリスクが高まります。
特に入浴時は脱衣所や浴室を事前に暖めておくことが重要です。
▼参考リンク
「寒暖差疲労」とは(外部リンク)
▼関連リンク
『間違った温活』がヒートショックを招く?知っておきたい注意点と予防法
すぐにできる温活

寒い季節は暖房器具に頼りがちですが、本来、人の体には適切な温活習慣を取り入れることで、冷えに負けない体温維持機能を高める力があります。
ここでは、日常生活の中で簡単に実践できる温活の方法を紹介します。
食事で温活
- ・根菜類(にんじん、ごぼう、大根)や生姜、唐辛子など体を温める食材を積極的に摂る
- ・温かいスープや味噌汁を食事に取り入れる
- ・カフェインの摂りすぎを避け、白湯や生姜湯を飲む
▼関連リンク
冷え対策に必見!!温活にオススメのカラダを温める食べ物とは??
運動で温活
- ・ウォーキングやストレッチ、ヨガなど軽めの運動を毎日続ける
- ・寒い日は家の中でスクワットや軽い筋トレをする

入浴で温活
- ・38~40℃のぬるめのお湯に10~15分ほどゆっくり浸かる
- ・炭酸入浴剤や生姜・よもぎ風呂などを活用とリラックス効果も高まります
▼関連リンク
汗活でデトックス!お風呂で効果的に汗をかいて、疲れをリセットしよう♪
まとめ
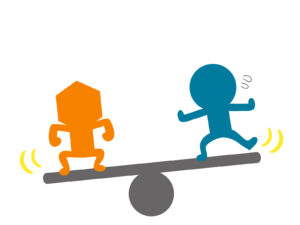
冬の寒さ対策には、”暖房器具の適切な使用”と『温活』の両方を意識することが大切です。
暖房器具に頼りすぎず、食事や運動、入浴などの温活習慣を取り入れることで、体温調節機能を維持し、健康的に冬を過ごしましょう。
特に急激な温度変化は体に負担をかけるため、室温や湿度の管理を意識しつつ、大きな不快感を抱かない範囲で、体感温度に頼りすぎず適切な温度調整を行うことが大切です。
自律神経のバランスが乱れると、過剰に冷やしたり暖めたりしやすくなるため、極端な温度設定は避け、自分に合った温活方法を見つけることが大切です。
例えば、毎日ゆっくりお風呂に浸かることで、体の芯から温める習慣をつけるのもオススメです。
暖房器具と温活を上手に組み合わせて、寒い冬を健康的に乗り切りましょう。
ぜひこちらもご覧ください👇
ミネラル×米ぬか×酵素×おもてなし ”米ぬか100% 酵素風呂ともしび”のココがすごい!!
公式SNS
◆関連記事
・体温が1℃上がると何が変わる?『温活』で得られるメリットとは?
・冷え性改善!体が温まるツボ押しマッサージで温活ライフを始めてみよう
・朝の一杯で腸もスッキリ!”カフェイン”を活かした賢い『腸活』の方法
・『米ぬか酵素風呂』で血流改善!高血圧・低血圧のケアに役立てよう
・善玉菌を増やして血糖値を安定!糖尿病・動脈硬化を予防する腸活の方法とは?
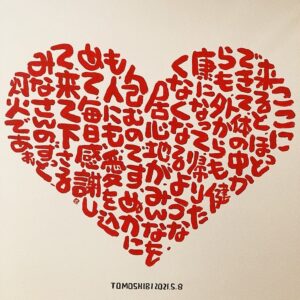
ご予約はこちら👇
体質改善をして
肌の悩みや、さまざまな病気を克服したい方はこちら👇
開業支援・運営コンサルティングを行っております。
詳細をご希望の方はお気軽にご相談ください。

店舗情報はこちら👇
〒583-0875
大阪府羽曳野市樫山255番地グランバレー1F
★お店の地図はコチラをご覧ください⇒Googleマップ
TEL :072-976-5377

営業時間/9:00〜19:00
mail:tomoshibi.kosoburo@gmail.com
ぜひお気軽にお問い合わせくださいね♪